《新築》完成までの流れ

(1)お問い合わせ
まずは、『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。
新築やリフォームのご要望はもちろん、世界にひとつだけの特別な家具が欲しい、お店を始めたいけれど何をすれば良いかわからない。何か楽しいことを始めたい、、など、ひとりで悩んでいませんか?
あなたの思いに寄り添い、一緒に考えます。どうぞお気軽にご相談ください。

(2)相談
その後、実際にお会いして、具体的な内容をお伺いし、私達の設計方針や業務の進め方、設計報酬などをご説明いたします。zoomなどオンラインでのリモート打ち合わせも対応しています。
初回の相談は無料ですので、安心してください。

(3)敷地調査・法令調査
新しいお住まいを建てる敷地が決まっている場合は、その敷地に関する調査を丁寧に行います。単純に法的な規制についての調査を行うだけでなく、その敷地の持つ魅力を見つけ出すための大切な調査です。
一般的にはマイナスとされて住まい造りには不利に感じる条件も、考え方次第では住まいに輝きを与えるプラスの条件であったりもします。まだ敷地が決まっていない方は、敷地選びから協力を致します。

(4)ご要望のリスニング
理想の住まいにするために、新しいお住まいに求めるご要望をリスニングさせて頂きます。
単純に「何部屋欲しい」「何畳がいい」という広さや数の条件を聞くだけではなく、「子供の頃はどのような生活をしていたか」「趣味の話」「好きな映画」「よく作る料理の話」などの、あなたの《好き》を聴かせて頂くことで、言葉にできない本当の要望を削り出していく重要な対話の時間だと考えています。

(5)基本構想+基本設計
ご要望をもとに、《コンセプト(デザインの指針)》を決め、そのコンセプトを元に間取りを決定していきます。単に間取りのパターンを出すのではなく、計画を貫く背骨となるような強いコンセプトを立てることで、”住まい”はより魅力的になると、私たちは考えています。
2週間に1度程度の打ち合わせを重ね、徐々に理想の”住まい”に近づけていきます。1ヶ月程度で満足のいくプランにたどり着く人もいれば、半年以上この期間に費やす人もいます。通常は3ヶ月程度の期間をかけたほうが後悔のない”住まい”造りになるのではないかと考えております。
第1案目の提案で私たちの提案力を判断して頂き、第2案目の作成に進むかどうかを判断して頂きます。次の提案作成に進まないと判断した際は、それまでにかかった実費分の精算をお願いしています。(概ね60,000円/回程度です。)

(6)工務店選び
ある程度、基本設計が進んできた段階で、工事を担当してくれそうな工務店を選びましょう。以下の可能性が考えられます。
・基本設計の内容を考慮し、その工事に適した工務店を一から探す。
・あなたが希望の工務店を指定する。(親戚や知人が工務店を経営している等)
・ハリコノイヌ製作所と付き合いのある工務店を紹介する。

(7)概算見積もり
基本設計がまとまってきた段階で、《概算見積り》を行います。その工務店の経験からおおよその金額を算出してもらい、現状の計画に大きな問題がないかを確かめたほうが安心です。
この時点で、大きく予算から外れていた場合は、計画の変更や、工務店を選び直さなければならないこともあります。

(8)実施設計
概算見積りに問題がなく、希望のプランにたどり着いた時点で、《実施設計》という段階に進みます。
実施設計というのは、ミリ単位の精密さで建物をどのように作るかを検討し、図面を作成する段階です。工事中に問題が起きないように、この時点でしっかりとした細かな検討を行うことが私たちの仕事です。

(9)本見積り
完成した実施設計図をもとに、工務店に《本見積り》をしてもらいます。
概算見積りとは違い、ひとつひとつの部材のサイズや数を拾い出し、より精度の高い見積りです。ここで決定した金額が工事費となります。
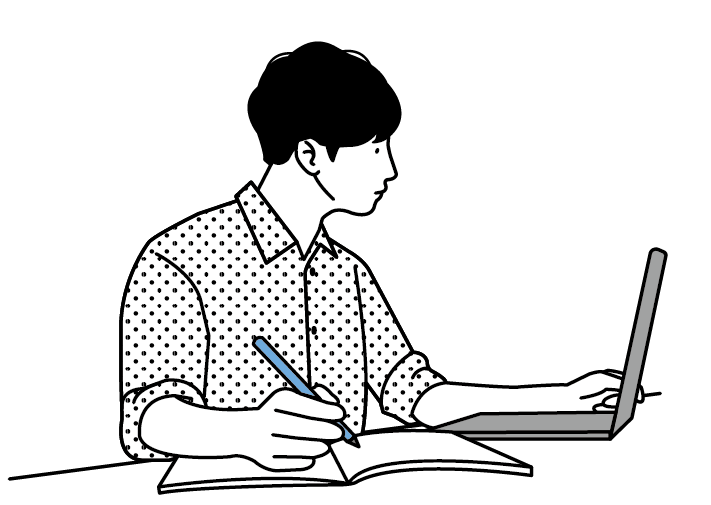
(10)見積り調整期間
本見積りの見積書をチェックする期間です。
私たちは、「材料が無駄に多く見積もられていないか」「選んだものがきちんと見積もられているか」「手間賃が過剰に多く設定されていないか」等をチェックし、見積書におかしなところがあれば工務店に修正してもらいます。
そのチェックを終えた後も金額が予算オーバーしている場合には、予算内に納めるための調整をしなければなりません。ここでは、何かを小さくしたり、一度決めたものを諦めたりしなければならず、住まい造りの中で最も苦しい期間ともいえます。
しかし、自分たちの生活の中に本当に必要なものを残し、優先順位の低いものをなくしていく作業の中で、大切なものを強く意識することで、その後の生活がより魅力的なものになることも多々あります。辛さもありますが、私たちも元の計画の魅力を損なわないよう一生懸命、減額のアイデアを考えますので、ともに乗り切りましょう。

(11)確認申請
工事を始める前には、役所か指定確認検査機関に対して《確認申請》を行い、計画している建物が法令を遵守していることを確認してもらう必要があります。確認済証が交付されれば、無事に工事に進むことができます。
私たちは基本設計や実施設計の最中にも、役所や指定確認検査機関に足を運び、随時事前の相談を行いながら計画を進めますが、時折、確認申請時に小さな修正を求められることがあります。その場合には、元の計画の魅力が損なわれない方法を考えます。
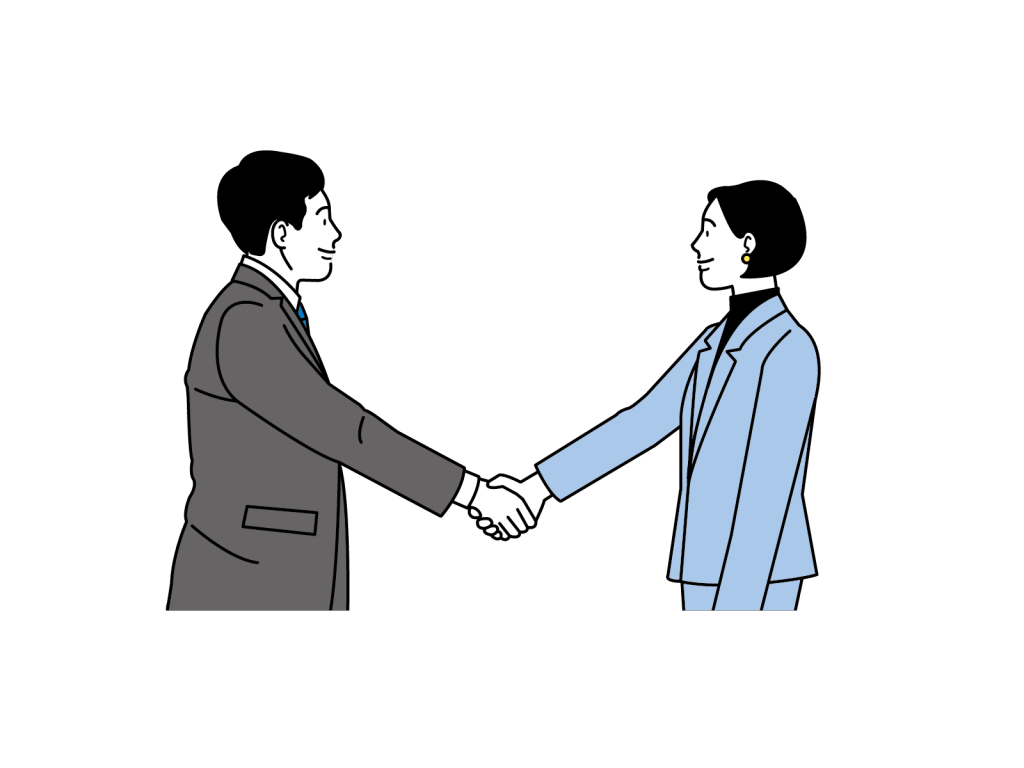
(12)契約
工事費が予算内に納まり、確認済証が交付されたら、いよいよ工事に進みます。その前にしなければならないのが、工務店との《建設工事請負契約》です。
この契約は、『この金額で』『この期日までに』『この図面に書かれている建物を完成させる』という、あなたと工務店との契約です。私たちは、事前に契約書の内容を精査し、建て主側に不利な条件が含まれていないかなどをチェックします。
あなたと私たち設計事務所との間には、『設計委託契約』とは別に『工事監理契約』を行うことにより、工事中に、工務店が設計図の通りに作っているかどうかをチェックする役割を担当します。
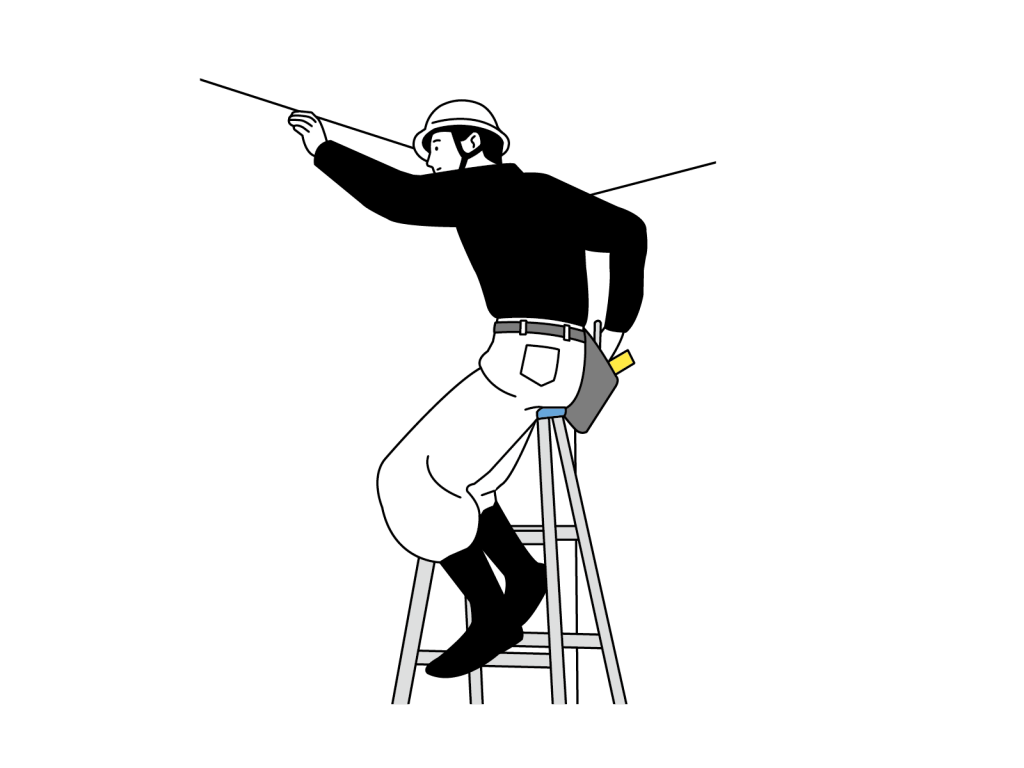
(13)工事
工務店との契約を完了したら、いよいよ工事が始まります。
工事前には、近隣挨拶や地鎮祭、工事中には上棟式などやるべきことが多々あります。
絶対にやらなければならないと決められているわけではないので、私たちは、「一般的にはこのようにする人が多い」と言ったアドバイスをさせて頂き、諸々の協力をさせて頂きます。

(14)竣工検査
工事が完了した際には、役所か指定確認検査機関による《完了検査》を受けます。
ここで、確認申請の提出書類通りの建物が実際に建てられているかをチェックされます。無事に検査に通ると、完了検査済証が交付されます。しかし、完了検査でチェックされるのは法的なことだけです。それ以外の建物の美観や機能性については別に検査を行います。
まず、工務店に対して《施工者による竣工検査》をするよう促し、建物の品質に問題がないかをチェックし、問題があれば修是正工事をしてもらいます。次に、私たちが設計者の立場で《設計による竣工検査》を行い、建物の品質に問題がないかをチェックし、問題があれば是正工事をしてもらいます。最後に、実際にその建物に住むことになるあなたの目で、最終チェックをして頂き、問題があれば是正工事をしてもらいます。
行政機関・施工者・設計者・建て主の4つの目でチェックすることにより、問題を見逃さないようにしているのです。
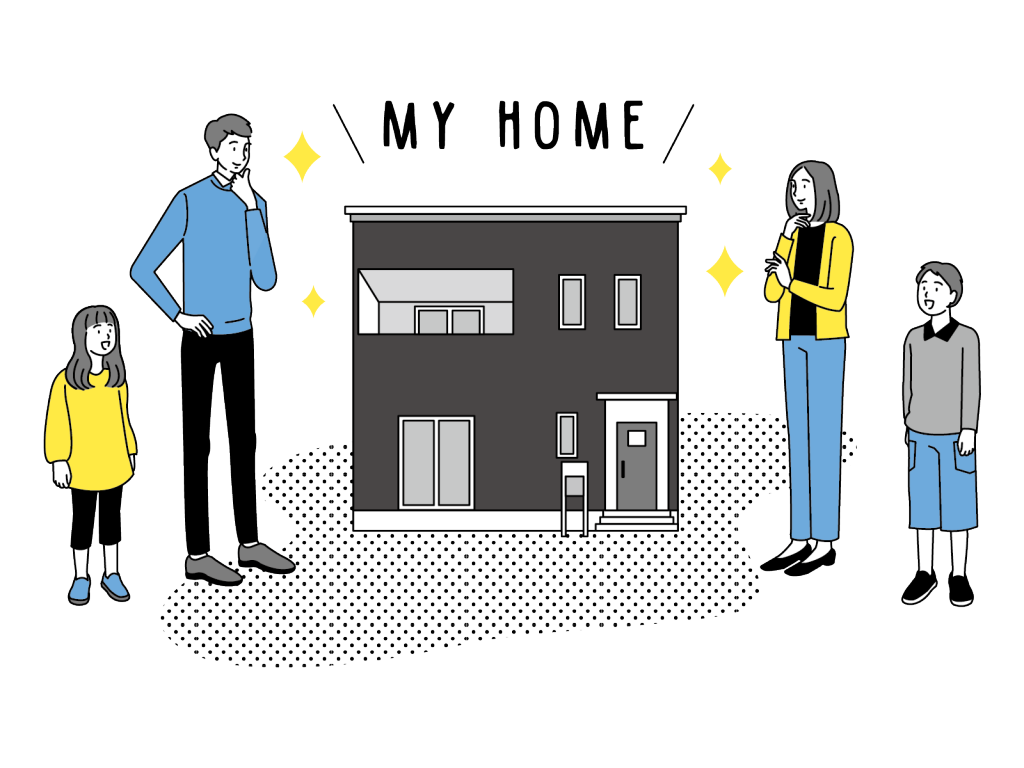
(15)引き渡し・引越し
全ての問題箇所が是正されたら、建物の《引き渡し》が行われます。
法的には工事が完了するまで建物は工務店の所有物なのです。引き渡しを機に工事中に使用していた鍵は破棄され、工事関係者であっても建物の中には入れなくなります。これで、新しい”住まい”はあなただけのものになるのです。
またこの時に、設置されている機器類の使用方法説明や、注意事項の説明などが行われます。引き渡しの後であれば、いつもで引越しが可能になります。
晴れて新しい生活のスタートです。